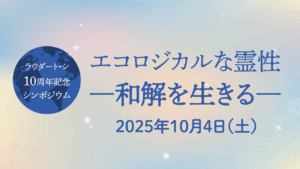被造物の季節 2025 エキュメニカル行事 Season of Creation

「被造物の季節(Season of Creation)」は、被造物の叫びに対し、全キリスト者でこぞって祈り、皆でこたえる、世界規模で行われるエキュメルカルな集中月間です。緊急性が高まる中、わたしたちは地球と、地球上にあるものとの平和を、見えるかたちで実現しなければなりません。正義が求めるのは悔い改めること、生きる姿勢と行動を変えることです。神の民としてともに働き、絶望ではなく希望を生み出していきましょう。
「被造物との平和」
「被造物の季節」エキュメニカル運営委員会提案が、毎年の「被造物の季節」がテーマを提案しています。
今年のテーマは「被造物との平和(Peace with Creation)」で、イザヤ書32章14–18節に着想を得たものです。
宮殿は捨てられ、町のにぎわいはうせ、見張りの塔のある砦の丘は、とこしえに裸の山となり、野ろばが喜び、家畜の群れが草をはむところとなる。ついに、我々の上に、霊が高い天から注がれる。荒れ野は園となり、園は森と見なされる。そのとき、荒れ野に公平が宿り、園に正義が住まう。正義が造り出すものは平和であり、正義が生み出すものは、とこしえに安らかな信頼である。わが民は平和の住みか、安らかな宿、憂いなき休息の場所に住まう。
イザヤ書32章14-18節
2025年のテーマを深める
2025年は「被造物との平和」(イザヤ32・14-18参照)をテーマに、心を合わせましょう。
教皇レオ14世も、今年の被造物を大切にする世界祈願日のメッセージ「希望と平和の種」において、「被造物の季節」に言及しつつ、イザヤの語る光景について説明しています。キリストにおいてわたしたちは種であること、それも「平和と希望の種」として、神の霊にうながされながら、荒れ野を園へと変えるために、公正と正義のために働く恵みをいただいていることを、教皇は語っておられます。ぜひ併せてお読みください。
また、英語にはなりますが、➡Celebration Guideには、この月間を過ごすための豊かなヒントが紹介されています。以下、「テーマ解説」部分の参考訳をご紹介いたします。
被造界に及ぶ戦争
「宮殿は捨てられ、町のにぎわいはうせ、見張りの塔のある砦の丘は、とこしえに裸の山となり、野ろばが喜び、家畜の群れが草をはむ所となる」(イザヤ32・14)。
預言者イザヤは、平和を失った被造界の荒廃した姿を描いています。それは、不正義や、神と人間との崩れた関係に起因しています。荒れ果てた都市や荒地の様子は、人間の活動が地球にもたらしうる破壊的影響を映し出しています。動物たちは、かつて人間だけが暮らしていた領域に入り込み、あたかも人間の居住によって本来のすみかを追われていたかのように、その場所を占拠し始めます。動物たちが草をはむ場となる(イザヤ32・14)のは、それ自体はよいことではありますが、そこには、人間が衝突の末にその地を退去せざるをえなくなるという代償が伴っているのです。
神の創造の計画は、本来、正義と平和を基盤とするものでした。ですが人間の罪がその秩序を損ない、被造界―豪奢な邸宅から貧しい農地、森や海に至るまで――は荒廃の一途をたどっていますす。イザヤは、人間が被造界との調和から離反した結果を、鮮やかに描き出しているのです。そして、遺棄され、朽ちていく見張り塔や宮殿が示すのは、戦争はいずれ神によって打ち砕かれるということです。
平和とは、単に戦争がない状態以上のものです。ヘブライ語聖書においてシャローム(=平和)は、はるかに深い意味をもっています。それは、争いがないということにとどまらず、イザヤの幻視に描かれているように、壊れた関係の完全な回復を指しています。この回復は、神との関係、自分自身との関係、人類家族との関係、そして他のすべての被造物との関係にまで及ぶものです。
歴史を通じて、人間の多くの活動が被造界の破壊に加担してきました。ですが今日、これまで以上に、人間の活動の一部が、被造物に対する戦争の様相を呈するようになっています。その影響は、局所的なものにとどまらず地球規模に拡大し、持続の不可能なライフスタイル、過剰な消費、恒常的な汚染、使い捨て文化という形態になって現れています。
この危機に対し、一部の者たちの責任はいっそう重いのです。富裕層の消費、搾取的なビジネスモデル、そして持続可能性よりも利益を優先する経済理論などです。汚染、健康危機、森林破壊、紛争地域での鉱物採掘は、状況をさらに悪化させています。
昨年、コロンビアのカリで開催された国連の生物多様性条約締約国会議(COP 16)は、「自然とともにある平和(Peace with Nature)」というテーマのもと、こうした問題の緊急性を浮き彫りにしました。
アッシジの聖フランシスコの「太陽の賛歌(Canticle of Creatures)」は、地球をわたしたちの姉妹であり母と呼んでいます。わたしたちが母なる地球をじっくりと見つめ、そこから学び、愛することをしなければ、どうして地球がわたしたちを養ってくれるでしょうか。わたしたちの相互のつながりを無視することは、いのちにかかわるこのかかわりを損ねるものです。
わたしたちの希望――正義が回復されたとき、被造界は平和を得るでしょう
「そのとき、荒れ野に公平が宿り、園に正義が住まう」(イザヤ32・16)。
平和に包まれた地球への希望があります。聖書では、希望とは能動的なものです。祈り、行動を必要とし、悔い改め(メタノイア)、連帯を通じた、被造界と創造主との和解が求められるものです。イザヤ書32章14〜18節は、正義が実現されたときにのみ神の民が住む、平和ある被造界を描きます。正義は平和をもたらし、大地の肥沃さを回復させます。「正義が造り出すものは平和であり、正義が生み出すものは、とこしえに安らかな信頼である。わが民は平和の住みか、安らかな宿、憂いなき休息の場所に住まう」(イザヤ32・14-18)。
被造物は、神の聖なる贈り物であり、わたしたち人間にそのケアが委ねられています。キリスト者は他の人々と協力しつつ、平和のうちに被造界を守り、はぐくんでいくよう求められています。そしてこの責任を、未来の世代に引き継ぐよう求められています。被造界が深く相互に結びついているがゆえに、平和は不可欠であると同時に、きわめて脆いものでもあるのです。
教皇フランシスコは、わたしたちにこう問います。「わたしたちの働きとあらゆる取り組みの目標はいかなるものか、わたしたちは地球から何を望まれているのか。生息可能な惑星を将来世代に残すことは、何よりもまず、わたしたちにかかっているのです」(『ラウダート・シ』160)。
教会は、気候、農業、生物多様性といった分野において、世界規模で取り組みに参画しています。その際には、神学的な土台に立ち、悔い改めと正義を求める預言的な要請に基づいて行動しています。いのちあるすべてのものとの和解、そして生きとし生けるもののための真の正義によってのみ、被造界は平和を得ることができ、イザヤの幻視(32・14-18)は実現するのです。
カイロスの時――ニケア信条1700年
「わたしは信じます。唯一の神、全能の父、天と地、見えるもの、見えないもの、すべてのものの造り主を。わたしは信じます。唯一の主イエス・キリストを信じます。すべてはこのかたによって造られました。わたしたちは信じます。主であり、いのちの与え主である聖霊を」(ニケア信条[i])。
2025年は、ニケア信条制定1700周年の記念の年です。325年以降、世界中のキリスト者は、ニケア信条を信仰箇条としてきました。共通の信仰を告白し、困難、不公平、分断のただ中にある世界で、キリスト者の信仰をあかしするよう求める信条です。ニケア信条は、諸教会を結ぶ平和と交わりのきずなであり続けてきました。被造物との平和を目指すわたしたちの働きも、この古く、しかも強固なエキュメニカルな交わりに連なるものです。これこそが、現代におけるニケア信条の一つの表れといえるでしょう。
ニケア信条によって確認されるのは、キリスト者は三一の神、御父と御子と聖霊を信じているということです。キリスト者であるわたしたちは、イザヤ書32章14~18節を、この三位一体の神への信仰に基づいて読みます。イザヤの予見した、荒れ野に注がれるいやしの霊は、聖霊であると識別します。イザヤがあかしする神の約束、「荒れ野に公平が宿り、園に正義が住まう」(イザヤ32・16)のことばに、御子の義とするわざを見いだします。
困難で、不公平で、分断されたこの世界に生きるわたしたちは、ニケアで打ち立てられた信仰告白と、教派を超えた交わりによって力づけられています。こうしてわたしたちはイザヤの呼びかけにこたえ、すべての被造物への神の平和の約束をあかしする、揺るぎない姿勢を貫いていくのです。ですから、争いと対立のただ中にあっても、神の約束を高らかに宣言しましょう。「正義が造り出すものは平和であり、正義が生み出すものは、とこしえに安らかな信頼である」(イザヤ32・17)。
行動への招き――「正義が造り出すものは平和」
神はわたしたちに、平和の作り手となるよう求めておられます(マタイ5・9)。わたしたちは平和のうちに生き、創造主を礼拝し、神の永遠の計画にかなう正義と持続可能性のある共同体の実現に向けて働くよう求められています。創造主とともに働かせていただく者として、わたしたちは、すべての被造物とともに生きる平和を体現する者とならなければなりません。
- 「わが民は安らかな宿に住まう」(18節)。神の平和は、無条件であり、すべての人と被造物のための公平と正義に根ざしています。平和が一部の少数の人にとどまることはありえません。
- 「園は森と見なされる」(15節)。神はすべての被造物を「よい」と断言されました。罪によって傷を負っていますが(創世記3・17–19)、生物多様性は神の寛大さと豊かさを映し出しています。キリストによって神は人間となられ、わたしたちに、被造界から学び、それを尊び、守るよう求めておられます。
- 「町のにぎわいはうせる」(14節)。戦争、気候変動、土地収奪などにより、土地と生計手段を失った地域共同体、また持続不可能な所業や負債に苦しむ人々の叫びに、祈りと行動をもってこたえましょう。
- 「ついに、われわれの上に、霊が高い天から注がれる」(15節)。神の霊は、わたしたちをエコロジカルな回心へと導き、宇宙家族の理解を深めてくださいます。わたしたちは考え方を変え、義を生き、こうした価値を次世代に伝えていかなければなりません。神の霊に駆り立てられて生じる結果は、より大きく、真に変革的なものであるはずです。わたしたちが目指すのは、争いが起こる前の状態に戻ることだけではないのです。
- 被造物との平和のためには、社会に訴えていく取り組みが求められます。イエスが教えてくださったのは、悔い改めと、修復をもたらす正義です。わたしたちは、断たれたかかわりを取り戻さなければなりません。それは、人間と地球、人間と他の被造物、人間と神とのかかわりです。
- 「正義が造り出すものは平和」(17節)。難題の数々に飲み込まれてしまいそうな中でも、キリストは気づかせてくださいます。「人間にできることではないが、神は何でもできる」(マタイ19・26)。希望は行動へと駆り立てます。祈り、識別、献身を通して、変化のための基盤を築くことができるのです。
- 神の平和は、わたしたちが正義、連帯、和解、被造物との調和のために働くときに現れます。変化には、忍耐、理解、そして信頼が求められます。
- 行動としては、意識醸成、持続可能性を考えた企画、環境美化キャンペーン、被造界を大切にすることは信仰の重要な側面であると示す環境教育なども含まれます。平和の実現に向けては、多様性を尊重しつつ協働をもって築いていくべきです。
- 「荒れ野は園となる」(15節)。森林の再生、河川の浄化、井戸の掘削といった平和構築の取り組みには、対立する人間集団を一つに結ぶ可能性もあります。
神の霊がわたしたちの上に注がれますように。そうしてわたしたちが、被造物との平和ために、ともに働くことができますように。
[i] 381年に「ニケア・コンスタンチノープル信条」となったものより引用。